バックロードホーン スピーカーの製作 (2019年7月9日〜)
PC机の上の、液晶ディスプレイの両脇にスピーカーを設置することにしました。
2〜3千円で売っている市販品にしようか、と思ったのですが
高校生の頃から、一度は作ってみたいと思っていた、バックロードホーン形の
スピーカーを自作することにしました。
早速、スピーカー製作の本を買って、設計方法を調べてみました。
|
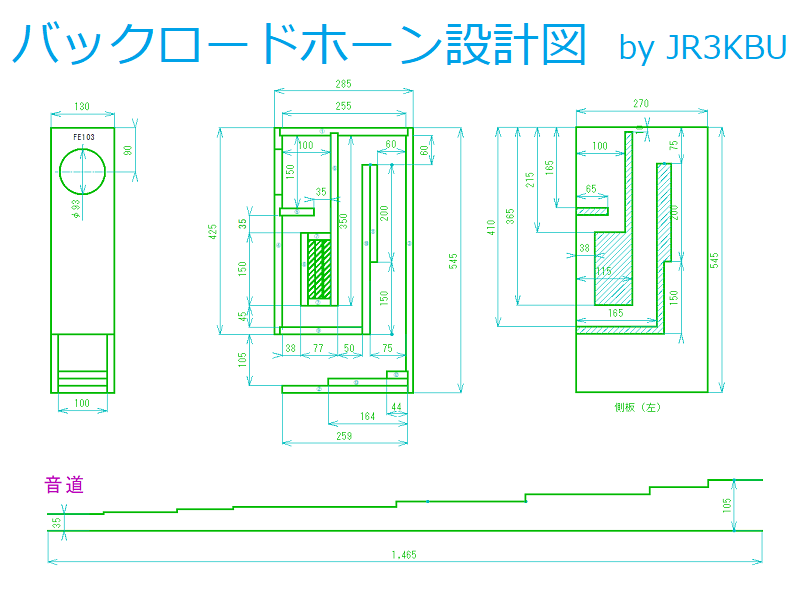 |
まずは大きさは、PC机とその机の上の棚の大きさに合わせて決めました。
高さは545mm、幅は130mm、奥行きは285mmです。
板厚は15mm。
音道の図は、音道のコーナー部分をいい加減に考えています。
音道の長さは、約1.5mとなりました。
|
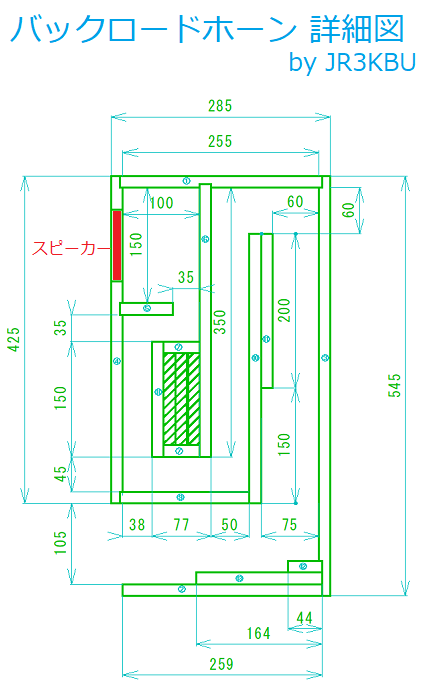 |
空気室(スピーカーの後ろの最初の空間)の容積は、1.5リットルとしました。
スロート(音道の最初の部分)の断面積は35平方cmにしました
(スピーカーの有効振動板面積50.24平方cmの70%です)。
そこから、およそ10cm進む毎に8%ずつ広がっていくようにしました。
|
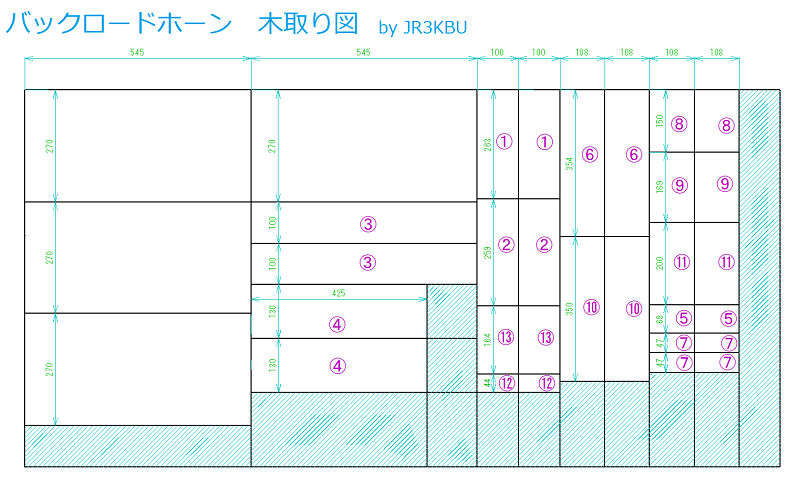 |
15mm厚のサブロク合板で、充分余裕をもって木取りできました。
これをホームセンター(京都府八幡のホームセンター『ムサシ』)でカットしてもらいました。
ムサシのカットサービスは精度が良く、また親身になってやってくれます。
1mmの誤差もありません。担当者が熟練の専門の方のようです。
私の家の近所のホムセンはアルバイトかパートタイマーの人のようで
ちょっと心配です(カット料金は安いのですが)。
クルマで30分以上かかるのですが、ムサシでカットしてもらうと安心です。
広い売り場で、板材もいろんな種類のものが豊富にあります。
ただ、機械の都合で90mm以下にカットできないそうで、上の12・5・7番の板は、
自分で電動丸ノコを使って切りました。
|
 |
トリマーで、溝切り・面取りをします。
梅雨明けの真夏で、最高気温=38℃になるような天気で、
午前中だけ作業しました(38℃の炎天下では死んでしまう)。
大量の「おがくず」が出るので、室内では加工できないのです
(一度、室内でやって後悔しました。部屋全体が真っ白になります)。
音がうるさいので(マキタの静音モデルですが)、午前8時から開始して、
4時間程度です。麦わら帽子をかぶり、汗だくです。
1時間毎にポカリスウェットを飲み、冷房した部屋で扇風機フルパワーで
体を冷却しながら加工作業をしました。
|
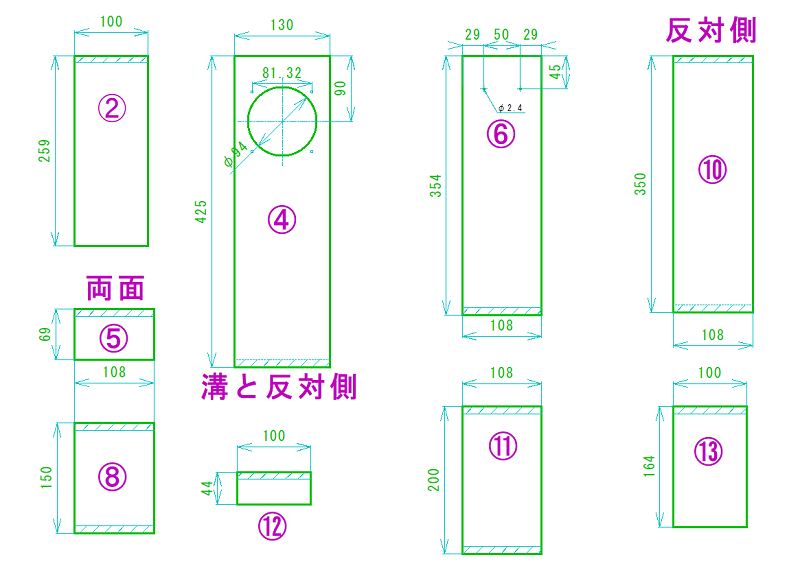 |
これが面取りする部分(ボウズ面加工)。
|
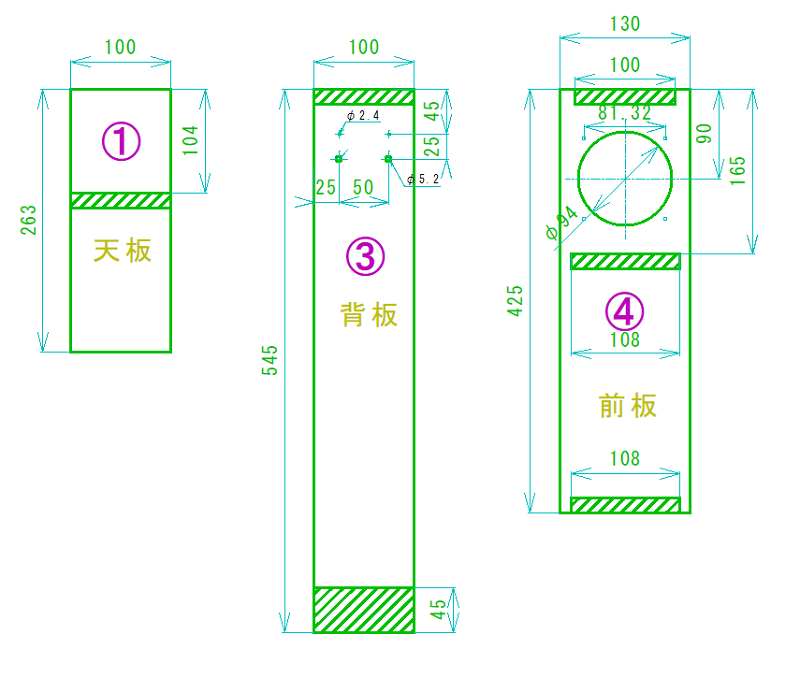 |
ハッチング部分を5mmの深さで溝加工します。
|
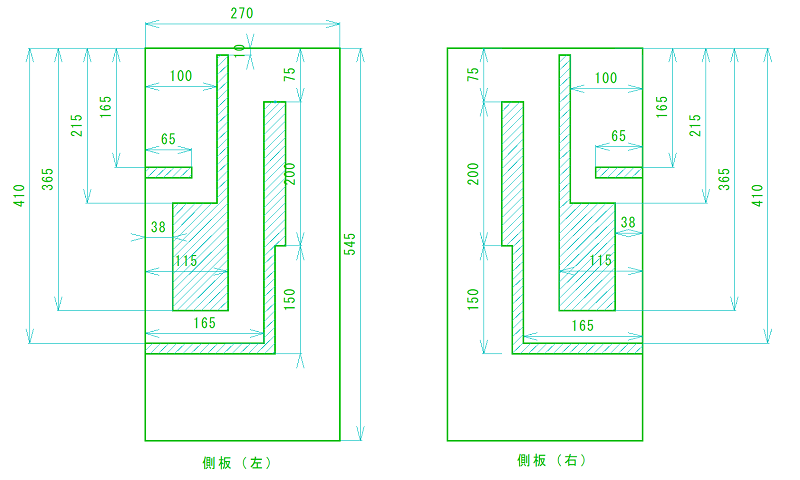 |
ここも5mmの深さで溝を彫ります。
左右対称です。
|
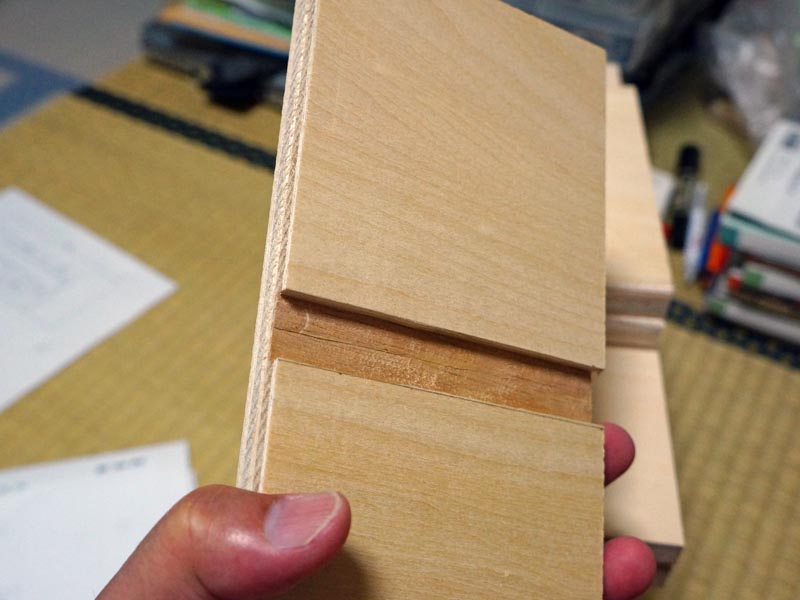 |
これが「大入れ」加工です。この溝に、別の板がすっぽりはまります。
|
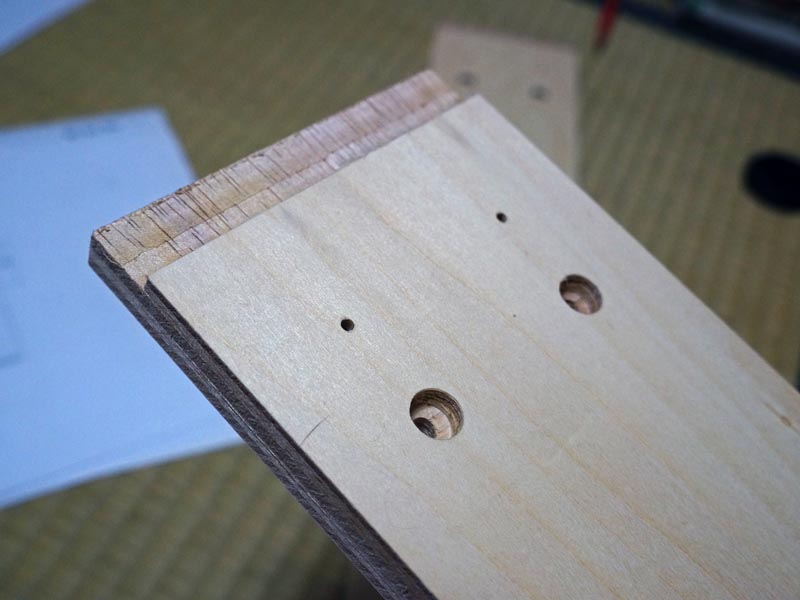 |
ここも同様です。
穴はスピーカー端子のためのものです。
|
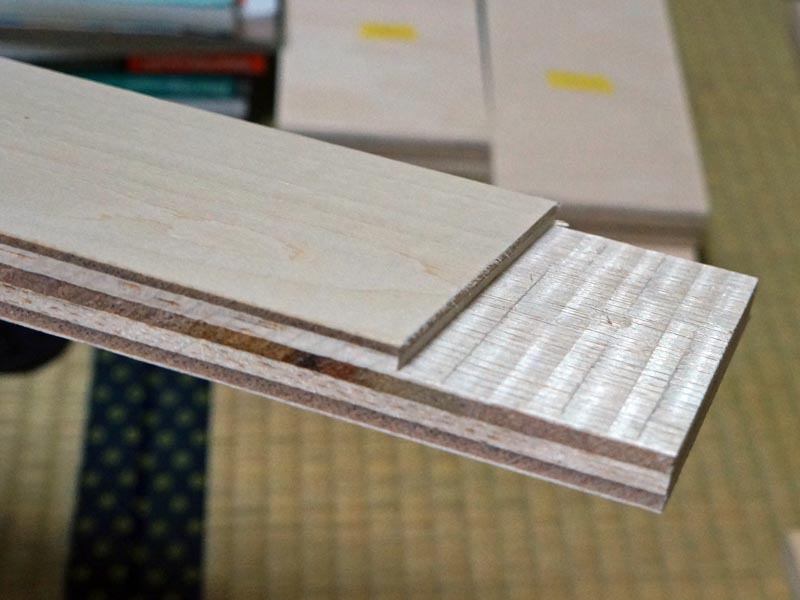 |
ここの大入れは、板が3枚分(底板)嵌ります。
|
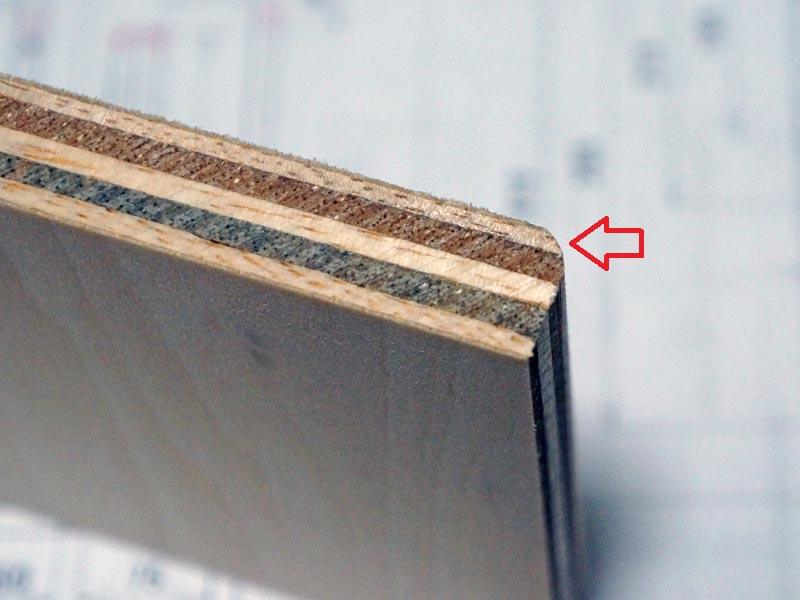 |
音道のエッジ部分は、このようにRを付けます。
R=6と、ちょっと少なかったです。
ただ、再加工する元気はありませんでした。
|
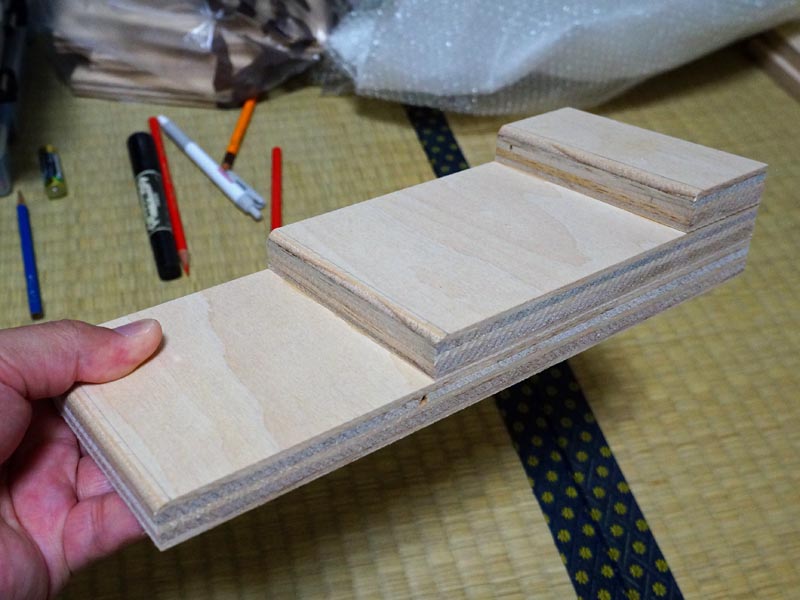 |
これは底板部分です。
3枚の板を貼り合わせました。
3枚ともエッジにRが付けてありますが、やっぱりちょっとRが小さかったです。
R=10が良かったです。
|
 |
土・日に板を加工して、
平日に少しずつ、部品を貼り合わせていきます。
|
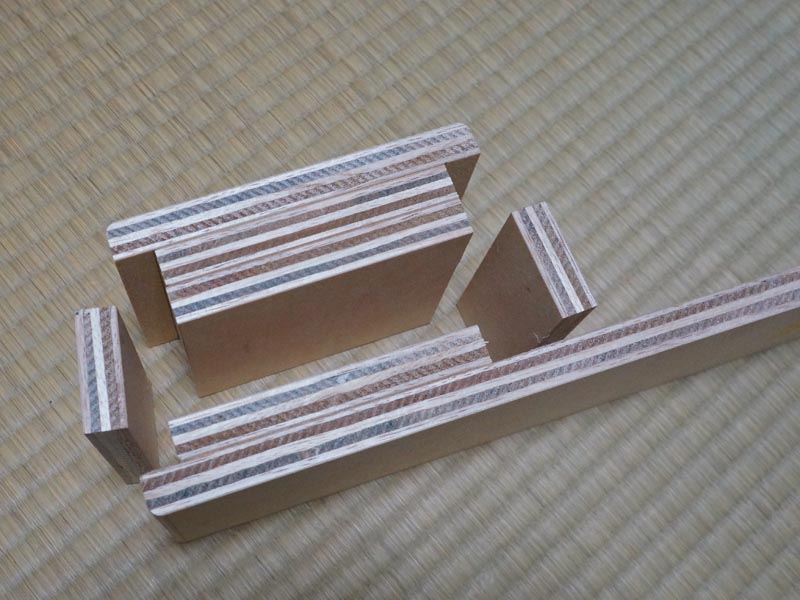 |
このように組み合わせます。
|
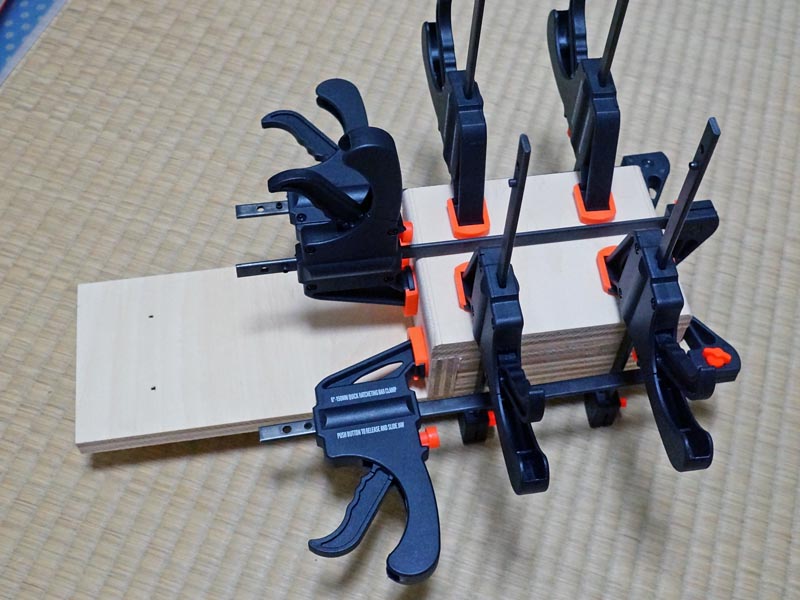 |
貼り合わせているところ。
|
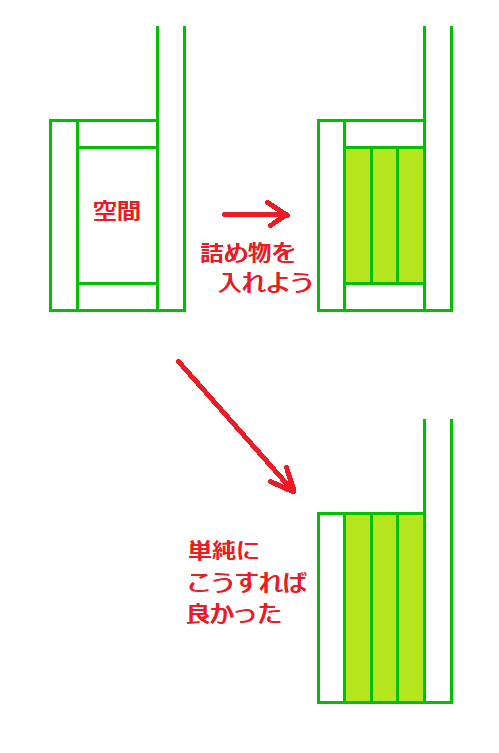 |
音道を区切る部分に空間があって、その空間が妙に共鳴してはマズいと思い、
詰め物をしたわけですが、
よく考えれば、もっと単純にできたのでした。
まあ、私の手間が増えただけで、どちらでも同じです。
|
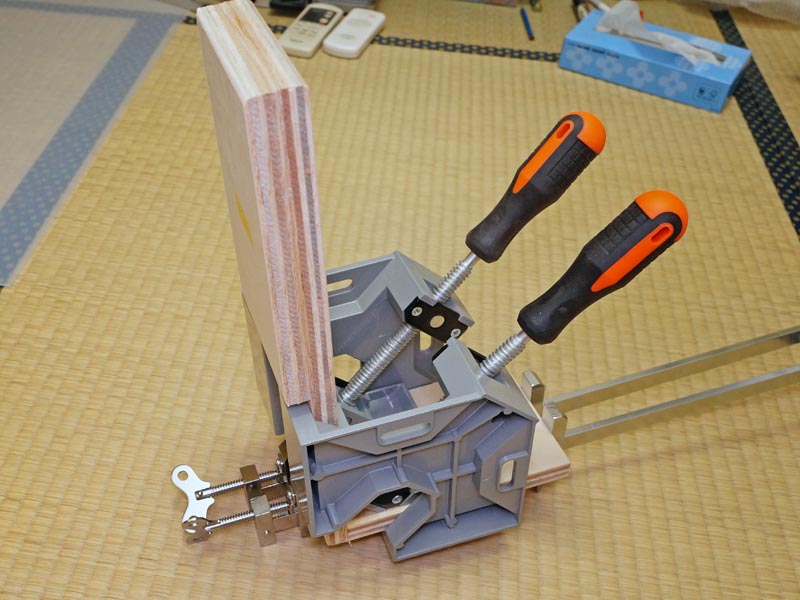 |
これは直角に貼り合わせています。
|
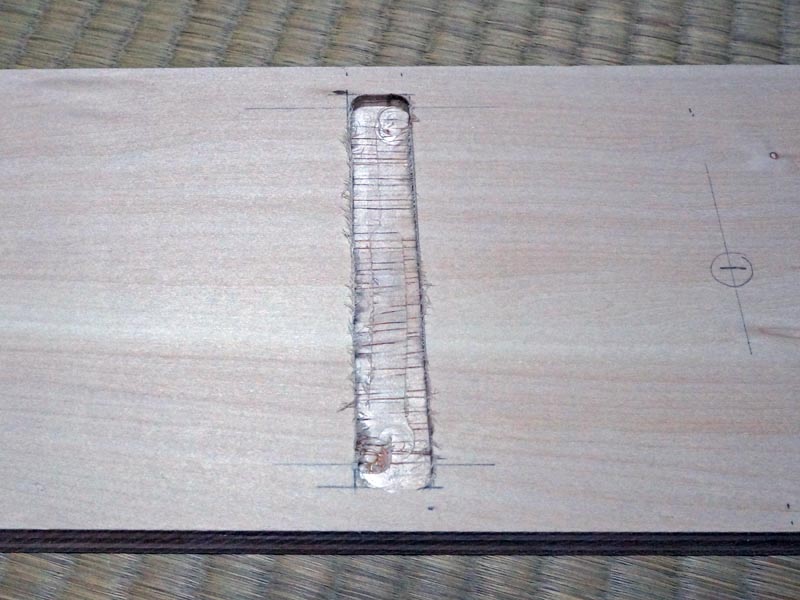 |
トリマーは刃物を回転させて削るので、隅は丸くなります。
|
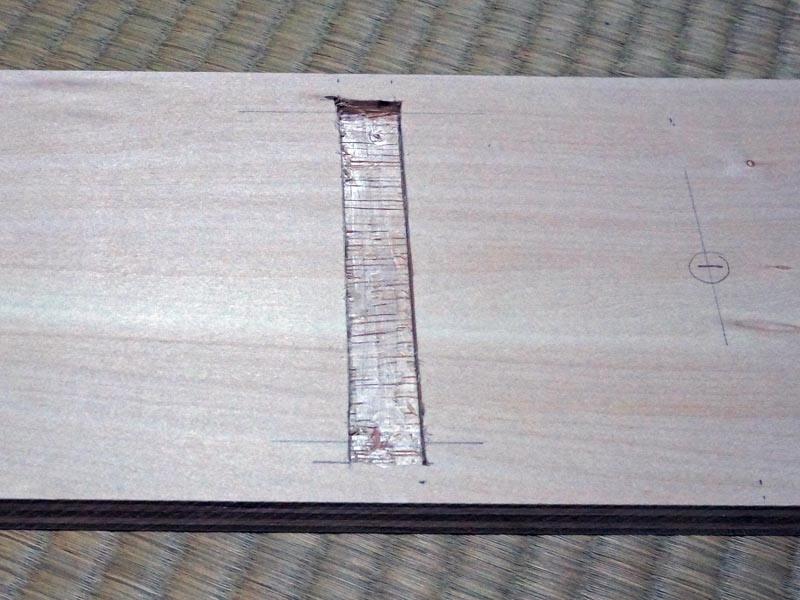 |
嵌る板は断面が長方形ですから、ノミで4隅を直角にしました。
ノミを使うのは中学生の時の技術家庭科以来です(40年以上ぶりの作業)。
|
 |
スピーカーを取り付ける穴を開けます。
|
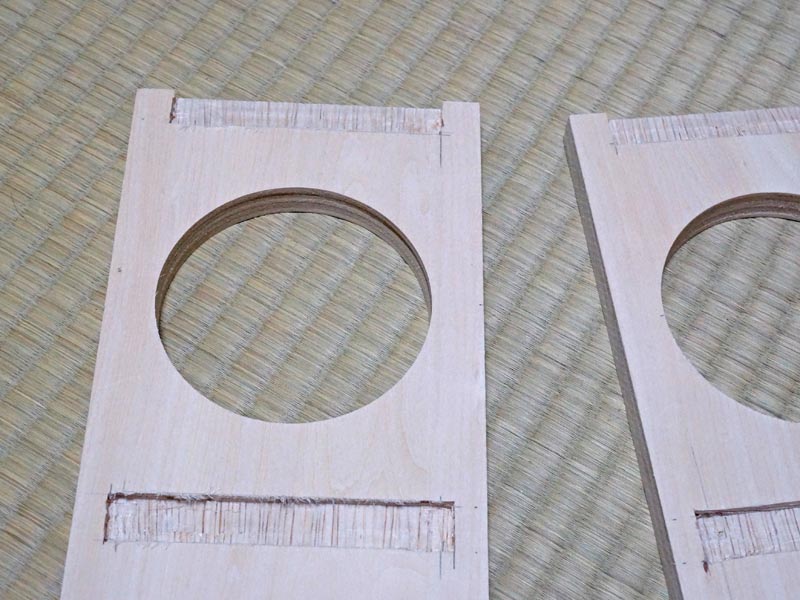 |
綺麗な丸穴を開けることができました。
一度に開けるのではなく、両面から開けるのがコツですね。
|
 |
新発売のスピーカー、Fostex社の「FE103NV」です。
初代の無印「FE103」は1964年に発売された超ロングセラーのスピーカーです。
何度かマイナーチェンジをしていて、「FE103En」の後継として、2019年7月末に
発売されたのが、この「FE103NV」です。
予約して買いました。届いたのは8月はじめでした。
「FE103NV」が新発売されるというのは全く知らず、
「バックロードホーンのスピーカーと言えば、Fostex社だよな」、と
ネット検索したら、この情報があったのです。
|
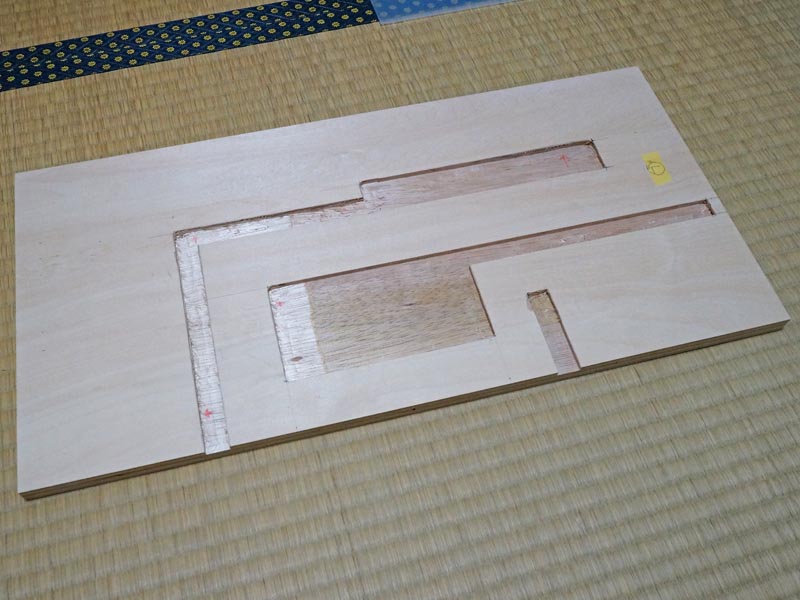 |
スピーカーが届き、早く箱を完成させたくなりました。
ようやく板の加工が終わり(この側板のトリマー加工が一番難儀でした)、
仮組みしてみました。
|
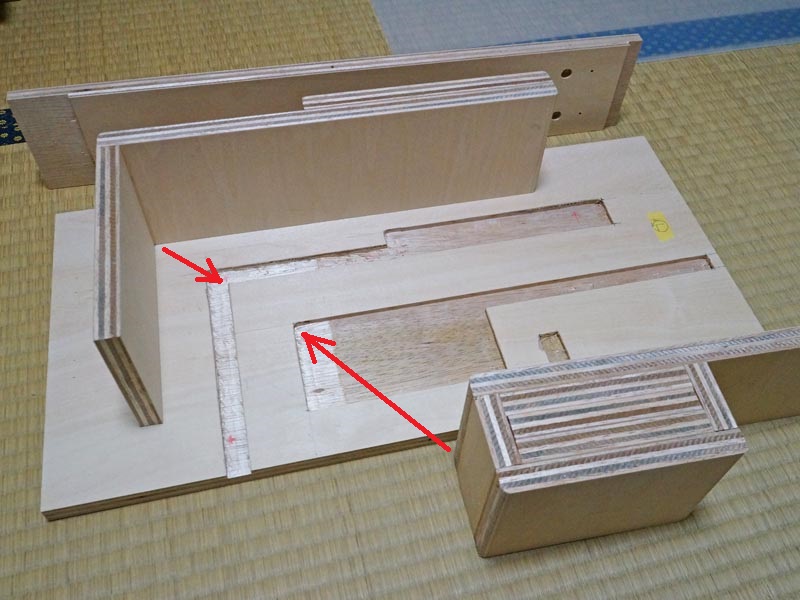 |
側板に部品(音道を区切るもの---2種類) を嵌めます。
|
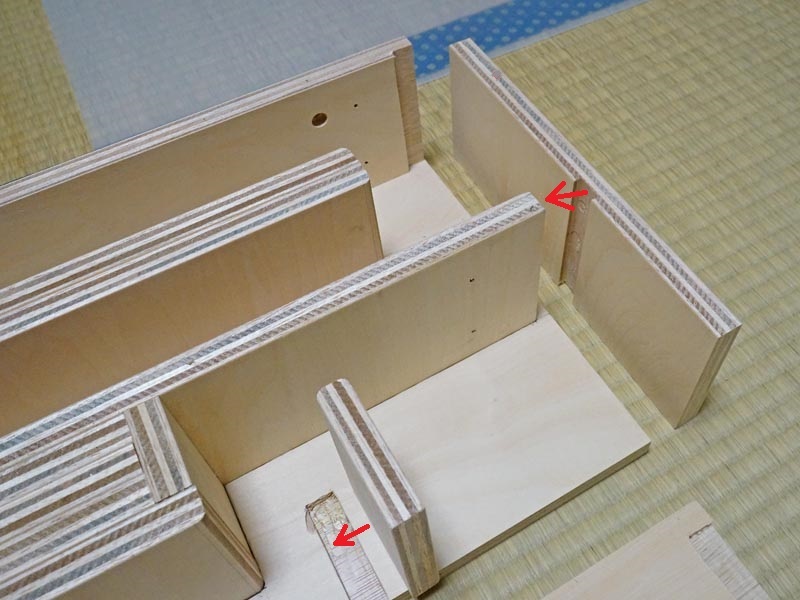 |
大きい板は天板、
小さい板は、スピーカーの空気室と音道を区切るものです。
|
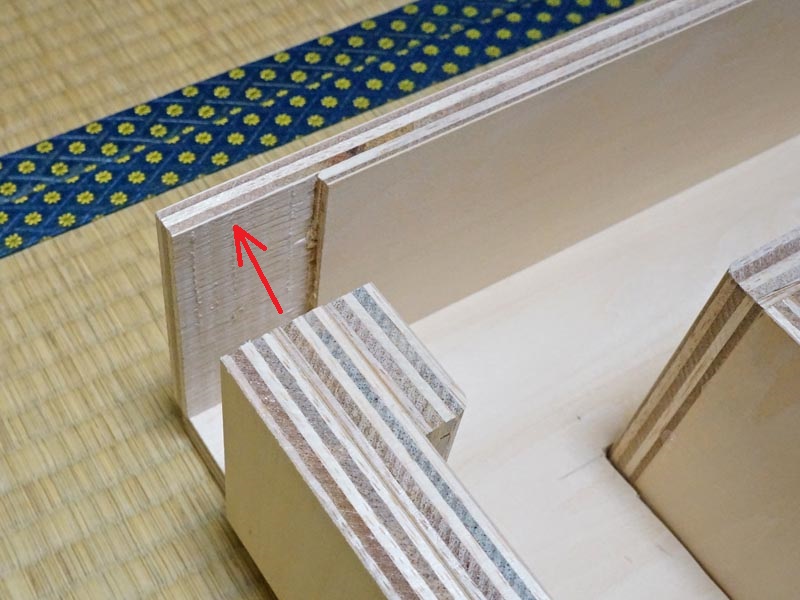 |
これは底板。
音道の最終コーナー部分です。
|
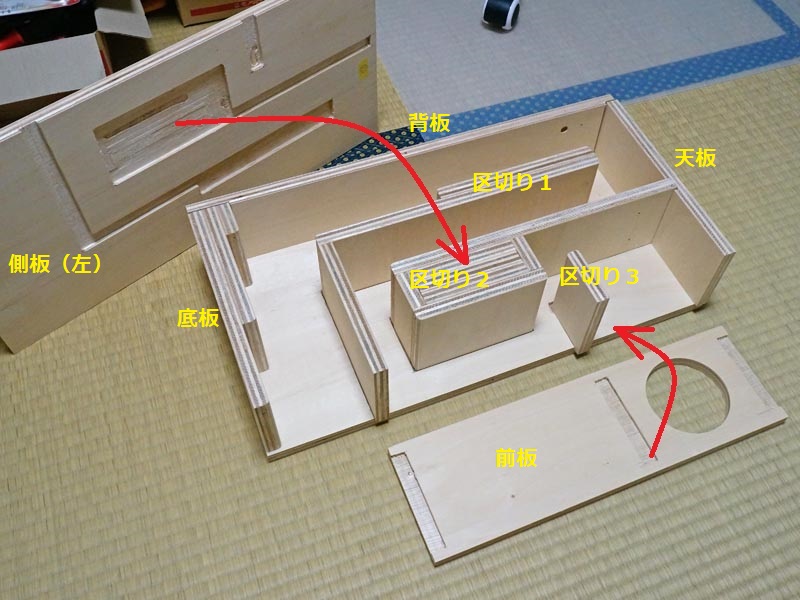 |
部品(天板・背板・底板・音道を区切るものを3つ)を載せたら、
もう1枚の側板と、前板(スピーカーを取り付ける板)を嵌めます。
|
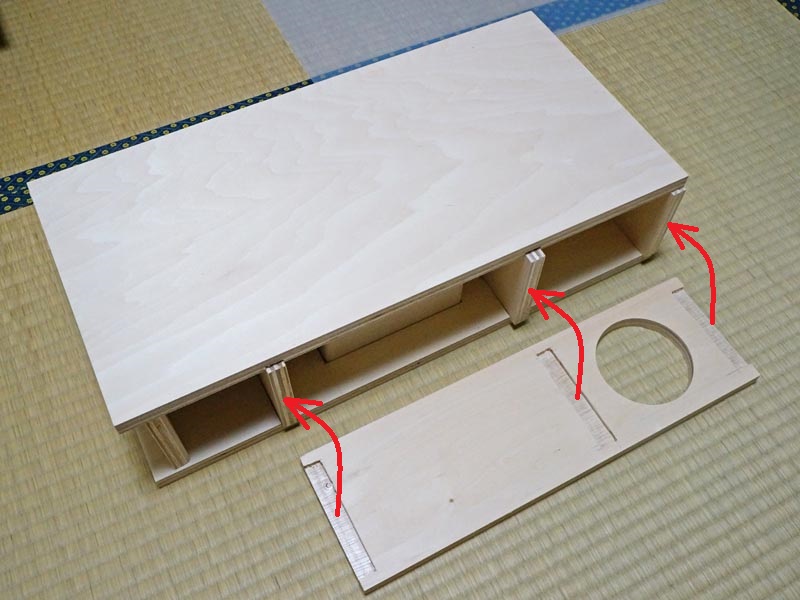 |
3箇所、板が4mm出っ張っていて、そこに前板を嵌めます。
すっぽりと嵌って、問題ありません。
|
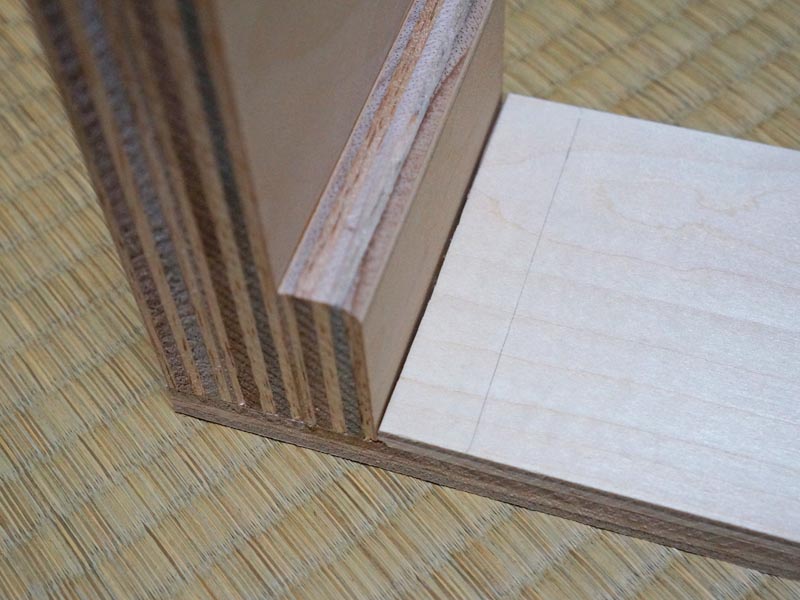 |
だいたい完成したのですが、音道が90度曲がる部分を緩やかにします。
|
 |
このように、三角の棒を接着します。
|
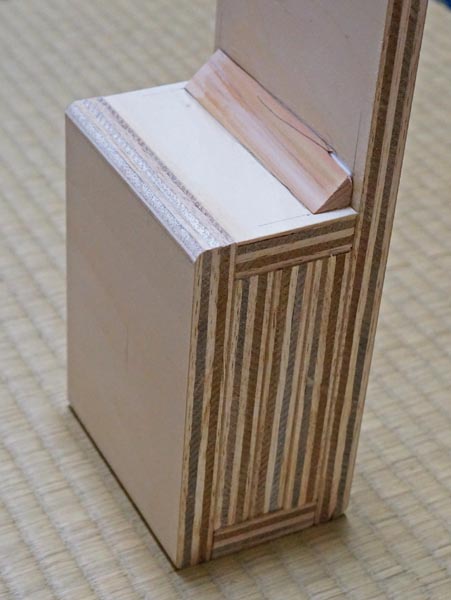 |
別の部分にも三角棒。
|
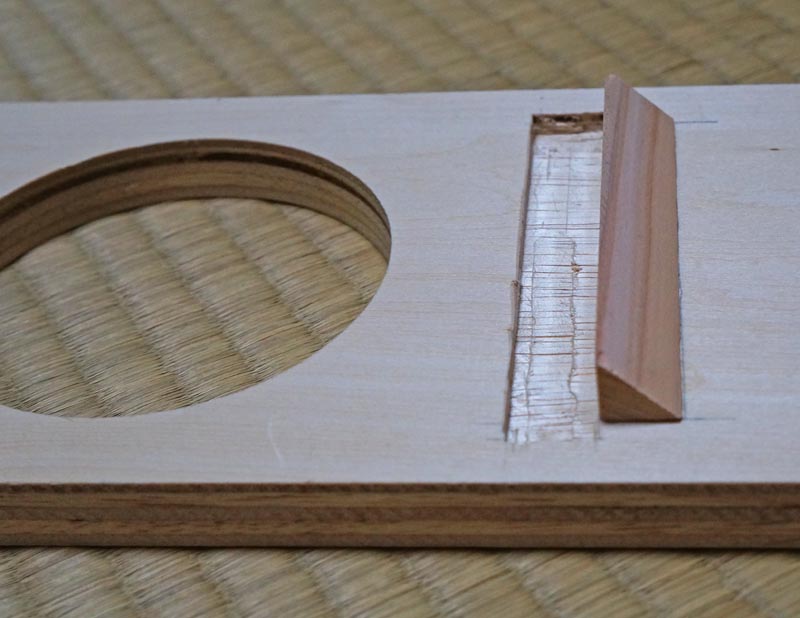 |
ここも。
|
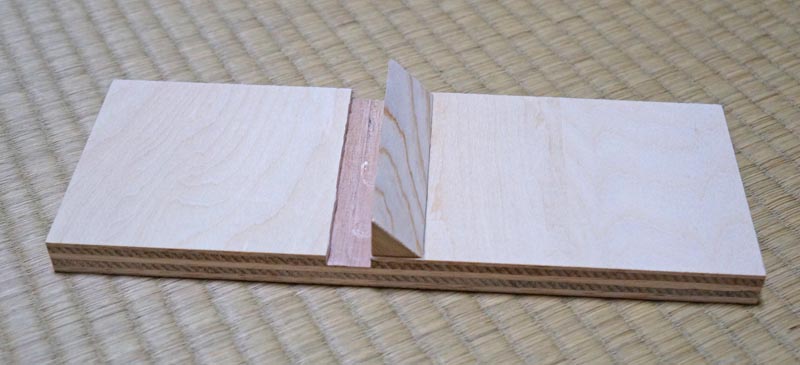 |
さらにここにも三角棒。
|
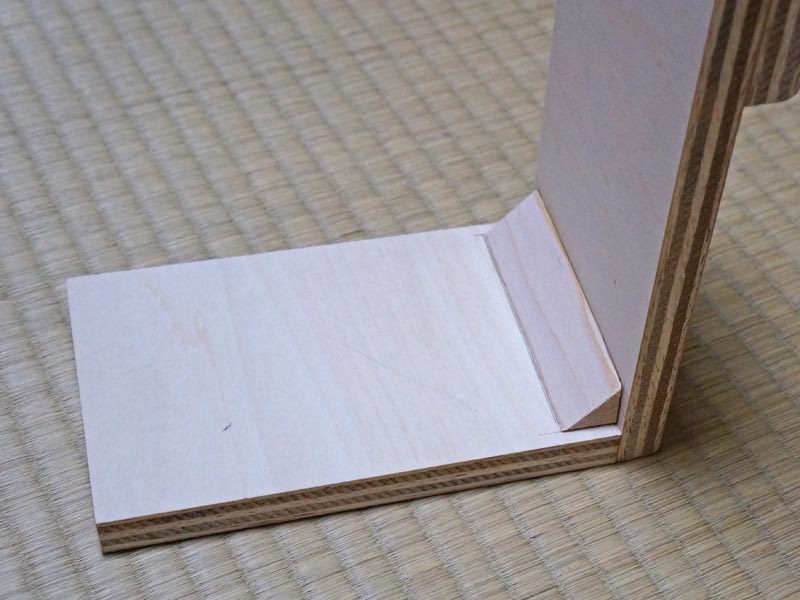 |
まだまだ。
|
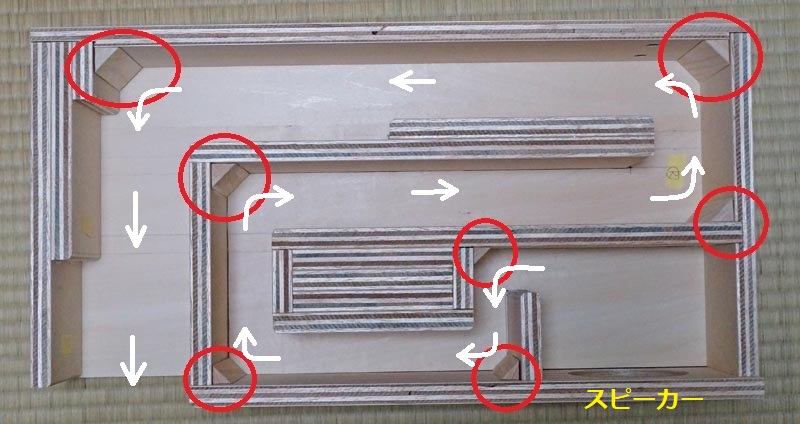 |
三角棒は7箇所に付けました。
音がスムーズに流れていく、、、はず。
|
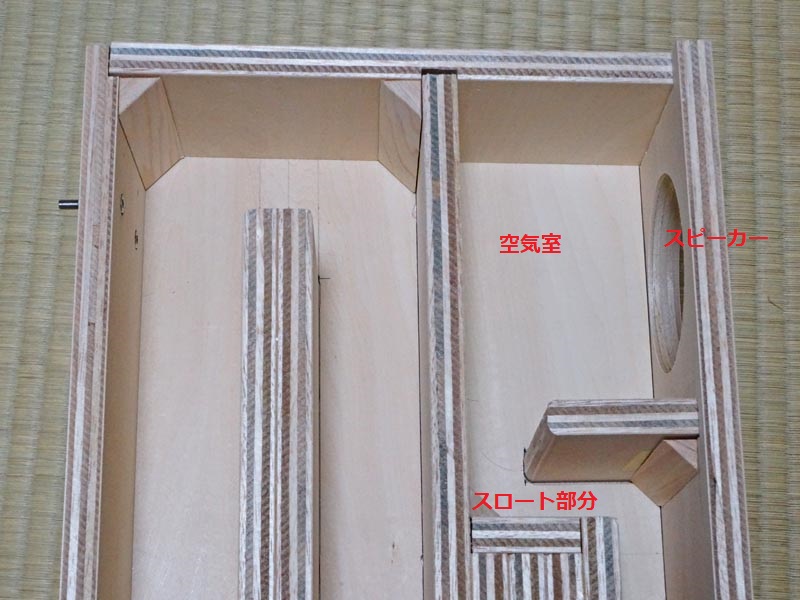 |
こんな感じです。
|
 |
いい感じです。
ここまでは接着していませんのでスキマが見えます。
|
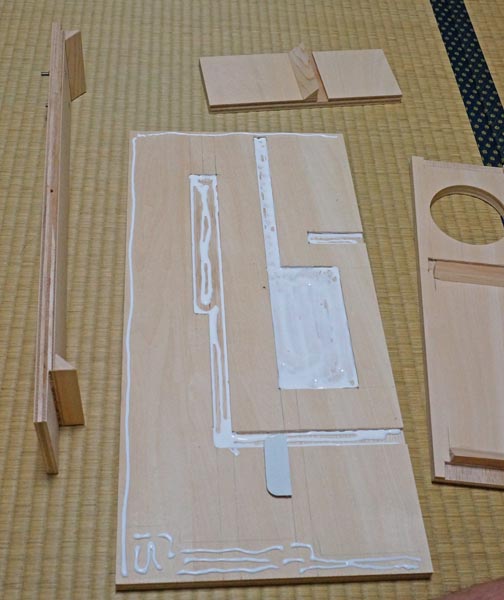 |
いよいよ、最終組み立てです。
接着してしまうので、もう中を見ることはできなくなります。
接着剤がどんどんなくなります。
スピーカー1個で1瓶弱使いました。まあ、1瓶200円ほどのものですが。
ヘラ(段ボールを切った時のカケラ)で均一に接着剤を均しました。
接合する部材の両方に、丁寧に接着剤を塗りました。
接着面にスキマがあると音が漏れてしまいます。溝を切ったのも、板同士が
密着するように、という気持ちです。
また、中途半端に接着するとビビリ音が出る可能性があるので(特に三角棒)、
注意して接着しました。接着剤をケチらないことですね。
|
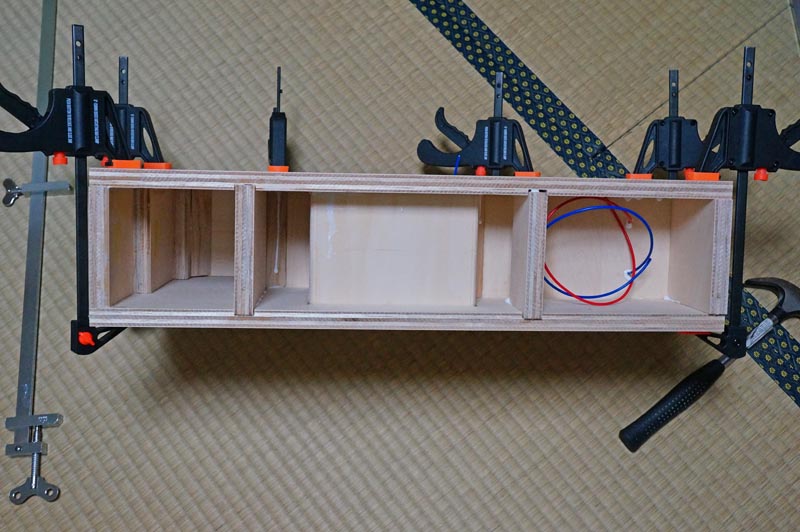 |
一番最後の前面板を嵌める前に、内部を撮っておきました。
はみ出た接着剤を拭っておきました。
|
 |
前面板を嵌めてたら、緊縛。
強力に締め付けます。
この状態で丸1日放置します。
|
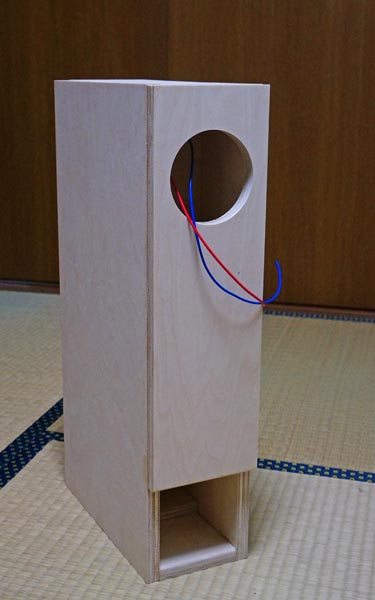 |
さて、箱は完成。
1ヶ月以上かかりました。
|
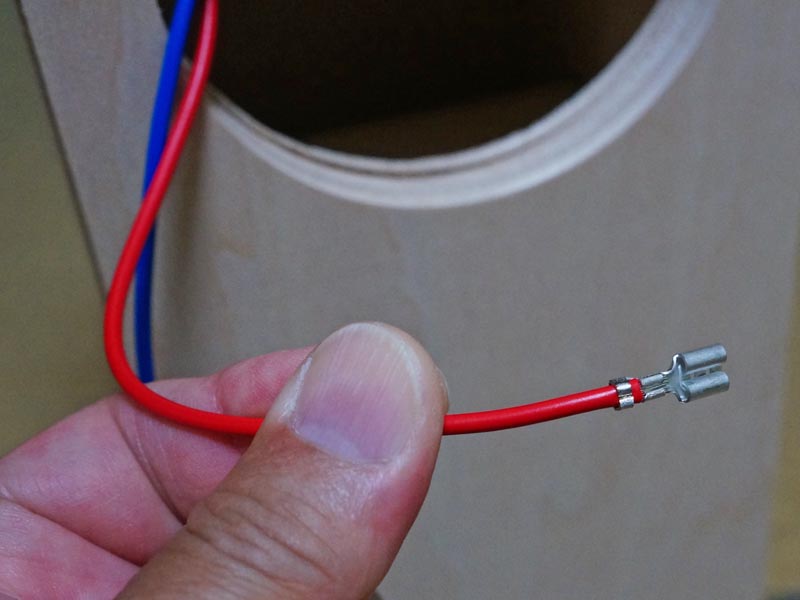 |
スピーカーに取り付けるファストン端子を圧着します。
|
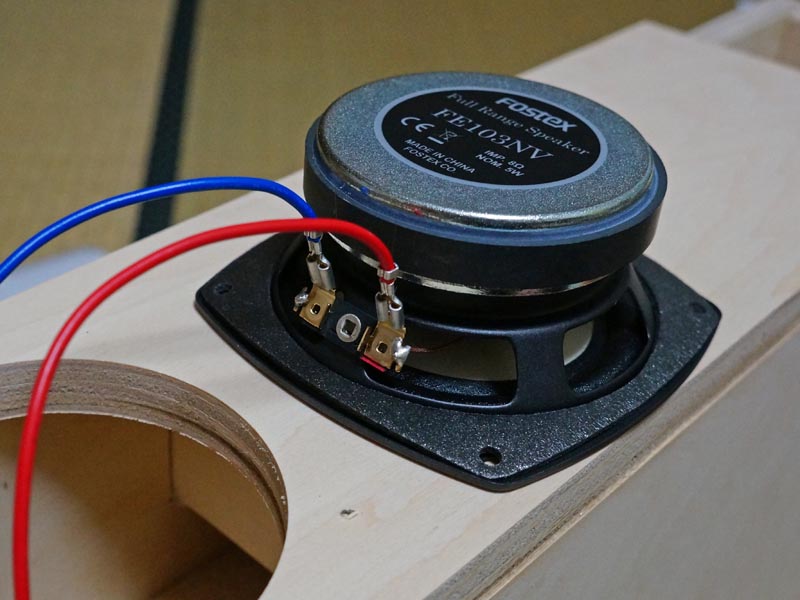 |
スピーカーに接続。
コーン紙を破ってしまわないか、ヒヤヒヤしました。
|
 |
スピーカーの取り付け完了。
かっこいい!
|
 |
背面のアンプへ繋ぐ部分です。手で持っている線がアンプに繋がります。
ステンレスのネジを裏から出るようにしてあります。
丸形圧着端子同士を、ナットで共締めします
(ネジに電流は流れません)。
|
 a a |
PC机にセットして、遂に完成。
お〜〜〜、素晴らしい。
1ヶ月間の苦労が実りました。
10cm径のスピーカーから出る低音とは思えません。迫力があります。
音道が長くないせいか、ハキハキと歯切れの良い低音です。
ボーカルの声がきらびやかです。
2時間以上時を忘れて聴いていました
(写っている時計を見ると9:45、昼ご飯の用意ができるまで聴いていました)。
|
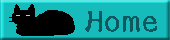 |
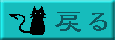 |